あくまでもひとつの意見としてご紹介します。
3月の後半に公開された映像ですが、多くの方に見ていただきたい。
【意見映像】政府は福島市に緊急避難命令を出すべきです
http://www.youtube.com/watch?v=iTEjE9XCctY
【意見映像】福島の土壌汚染はチェルノブイリ並みではないのですか
http://www.youtube.com/watch?v=_LtJKeTelmc&feature=related
これらの妥当性についてはご覧になった方それぞれの判断ということで。
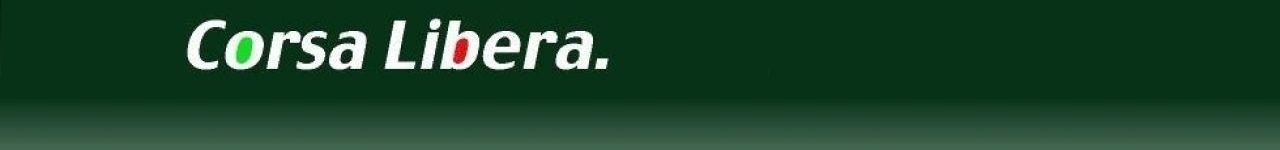
あくまでもひとつの意見としてご紹介します。
3月の後半に公開された映像ですが、多くの方に見ていただきたい。
【意見映像】政府は福島市に緊急避難命令を出すべきです
http://www.youtube.com/watch?v=iTEjE9XCctY
【意見映像】福島の土壌汚染はチェルノブイリ並みではないのですか
http://www.youtube.com/watch?v=_LtJKeTelmc&feature=related
これらの妥当性についてはご覧になった方それぞれの判断ということで。
こういうサイト、とてもありがたいです。
拙宅近傍の横浜市青葉区で個人で測定を行い、公開していただいているサイトです。
青葉台放射能測定マップ 2011年5月~
http://www.amorfon.com/radiationmap/
私見ですが、横浜市が磯子区のモニタリングポストで測定・公開している値(地上23m)は意味のないものではないと考えます。
ただし、あくまでも傾向を見る(そもそもそれが目的で設置されているものですから)ためのもので、線量に関しての判断材料のひとつと考えるべきでしょう。
また、上記サイトで公開されているのはハンディ型の線量計ですが、測定誤差が大きいということ(数分の一~数倍は誤差になり得るらしい)で、測定値のみを見て一喜一憂するのは妥当ではありません。(なので、上記サイトのように、いろいろな地点や条件で測定した結果を公開していただけるのはとてもありがたいのです)
放射線が人体に与える影響は間違いなくあることは事実なのですが、どの程度の線量を浴びた場合どうなるのかというのは、致死レベルはともかく、低線量の域では良く解っておらず、専門家の間でも議論されているようです。
結局、福島の原発事故の影響はあります。これは間違いない。
しかし、安全か否かは誰も判断ができない。というのも現実です。
自分の身と家族は自分自身でしか守れないということです。安全か否かの判断をを0か100かで求めるのではなく、自分自身で判断できるように、知恵をつけ情報を収集して生活するほかありません。
横浜市でも、線量について従来の環境科学研究所での測定(地表 23m)に加え、認可保育所(地表 0.5m)、小学校(地表 0.5m)・中学校(地表 1m)、公園(地表 0.5m)、都筑区役所、南部公園緑地事務所、環境科学研究所(地表 0.5m及び1m)といった場所での測定が順次開始され、測定値が公開されるようになってきました。
いろいろ言いたいことはないこともないのですが、一歩前進と思います。
ただ、保育所での測定値についてのコメントがあるのですが、疑問に思う点がありましたので、今回、横浜市のサイトの下記URIから市に対して質問を送りました。
◆◆「市民からの提案」◆◆ 横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/kocho/teian/
受付日の翌日から数えて14日以内に回答または状況の連絡がいただけるらしいです。また、「市民からの提案」のうち、「文書」又は「Eメール」で回答したものについては、市ホームページにおいて、ご提案やご意見の要旨とそれに対する横浜市の回答(対応状況)を原則として公表するらしいです。
回答が得られたり、公表されたことが判明したら、またご紹介したいと思います。
*以下、問い合わせ全文*
認可保育所の園庭における放射線量測定について疑問
3歳の子供をもつ親です。
いつも市のサイトを参考にさせていただいております。
日頃より、諸々の制約もあるとは思いますが、情報の提示に力を注いでいただき感謝いたします。
横浜市のサイト、たとえば下記URLにおいて疑問がありますので提案(質問)があります。ご回答をお願いいたします。
認可保育所の園庭における放射線量測定結果(6/20)
http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/unei/hou-sokutei/sokutei110620.html
このページ(6/16の測定結果のページも同様ですが)に以下のような説明があります。
*ここから*
●測定結果の説明
いずれの認可保育所の値も、本市の目標値である年間1mSv(ミリシーベルト)を下回り、利用者の健康に影響を与えるものではなく、年間を通じた園庭等での活動に支障はありません。
*ここまで*
放射線障害防止法によると、一般社会において、文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量で1mSv/年となっています。
質問ですが、
1)1mSv/年を規制値でなく、目標値とした根拠をご教示ください。
2)単純計算では1mSv/年以下とするのであれば、実効線量で0.114μSv/hです。最大値が出るところでは、γ線だけで線量限度に到達しますが、それでも安全とする根拠をご教示ください。
3)当該測定方法ではγ線の測定を行っておられますが、規制値は実効線量ですから、内部被曝分の評価も足さないといけないはずですが、それについてのご見解をいただきたい。
4)線量については、最大値はどの位置なのか(砂場?植え込み?池?など)どのような対策を行うと良いのか(良い可能性があるのか)といったアドバイスも含めて公開すべきと考えますがご見解をいただきたい。
以上、長くなり恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
年間1mSvという件については下記サイトにも記されています。
Blog vs. Media 時評
年間1mSvは法定の限度線量:遵法感覚はどうした
http://blog.dandoweb.com/?eid=123874
今回の福島第一原子力発電所の事故ですが、
以前から、今回の事故のような結果となることは想定されておりました。
先にご紹介した、武谷先生の「原子力発電」という本、これは1976年の本ですが、原子炉の緊急停止から、崩壊熱除去がうまくいかないとどうなるのか、もう40年も昔に想定され、計算されていたことなのです。
最近になって(それでもポツポツと少しずつ)情報が漏れるように伝わってきますが、まぁ福島第一の場合は最初の商用運転を行う、ということで、水質調査、気象、地質、海況、交通、人口分布などかなりの調査を行っています。
風向きとか、海流とかなんかは解っているんですよね。実は。
情報は探せば出てきます。
政府は一生懸命隠したいようですが、縦割り行政の悲しさ(平時であれば)というか、身内からも情報は出てきます。それが緊急リンクでも紹介しているKEKのサイトだったり、以下のような記事だったり。
この際です、少しずつ知恵をつけましょう。
政府やマスコミの言うことは(とても好意的に書くと)限りなく真っ黒なウソはなくても、せいぜいグレーであったり、きわめて一部のみで使えない情報ばかりです。
我々が知恵をつけていろいろな情報を分析するとウソもあぶりだされてくるはずです。
できるだけ正しいデータを集め、できるだけバイアスのかからない結論を見出して行動しようじゃありませんか。
【福島県飯舘村・現地レポート】
持続可能な村づくりを奪われた村――原子力災害の理不尽な実態
小澤祥司 ダイヤモンドオンライン
http://diamond.jp/articles/-/11978
冷却水の投入について東電はウソをついているのか。(妥当な量にはなっているみたいですが)
原子炉内が崩壊熱のみによって加熱されている場合に必要な水の投入量の推定
東北大学 流体科学研究所 圓山・小宮研究室
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/maru/atom/HTCRep/HTCRep.1.4.pdf
あと、お嫌いの方もいらっしゃるようですが、比較的、良心的な情報を発信されていると思います。
武田邦彦(中部大学)
http://takedanet.com/
うちのAstraの4回目の車検(うちに来てから2回目)の車検も無事終了、
のびのびになっていた夏タイアへの換装も含め、本日戻ってきました。
特に消耗部品関係も問題なく、チェックだけで済んだとのことでお財布にもやさしい結果でした。よかったよかった。